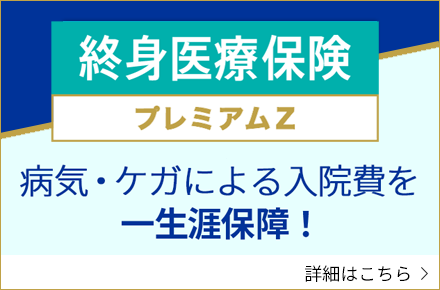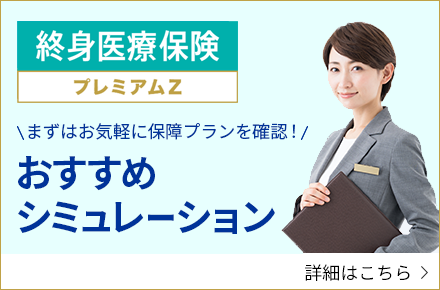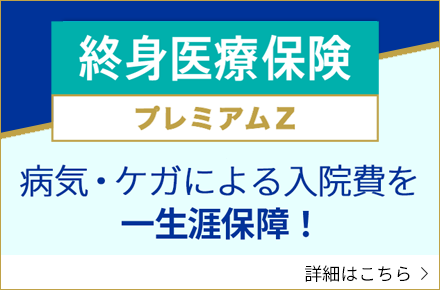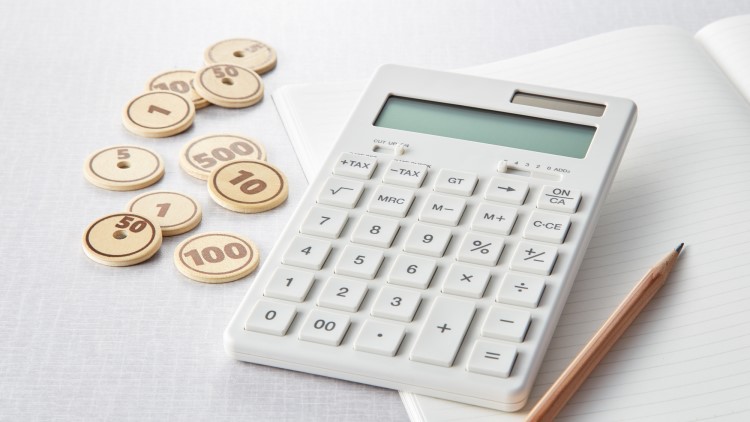医療保険コラム
医療保険の加入や見直しを検討している方や、医療保険の基礎知識を知りたい方へ。
選ぶ時のポイントや、必要な金額など詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。
医療保険の受取人は誰がなる?指定のルールから税金の違いまで詳しく解説
医療保険に加入する際は、申込時に給付金の「受取人」を決める必要があります。受取人には誰を指定できるのでしょうか。ここでは、医療保険の給付金を受け取るときに問題が起きないよう、受取人の決め方や税金の仕組みについて詳しく解説します。 …
高齢者に医療保険は必要?活用すべき公的制度や選び方のコツをご紹介
高齢者を対象とした医療保険の選び方や考え方についてご紹介します。医療保険が必要かどうかの判断と、適切な医療保険の選択のために、ぜひ参考にしてくだ さい。 …
差額ベッド代とは?入院時の個室代や希望割合について解説!
「病院の個室に入院すると、「差額ベッド代」という追加料金が発生します。こちらのコラムでは、差額ベッド代の基本的な内容や、差額ベッド代がかからないケース、差額ベッド代への備え方について解説します。 …
医療保険の通院保障は必要?知っておきたい通院費の基礎知識
「通院保障」は、医療保険に付加できる特約の1つです。医療保険へ加入する際、「通院保障はつけた方がいいのだろうか」と悩む人もいるでしょう。ここでは、通院保障の基礎知識や重要性について詳しく解説します。ぜひ通院保障の付加を判断する際の参考にしてみてください。 …
定期タイプと終身タイプ、医療保険ではどちらを選ぶ?
医療保険にもさまざまな商品がありますが、保険期間(保障される期間)の違いによって、大きく「定期タイプ(定期医療保険)」と「終身タイプ(終身医療保険)」の2つのタイプに分けることができます。定期タイプと …
医療保険の加入・見直しのタイミングっていつ?
医療保険は、入院や手術をした際に給付金を受け取れる保険です。若いうちは病気になることも少ないため、医療保険にいつ加入したらよいのか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか。本記事では、医療保険の加入や見直しのタイミングについて…
医療保険の必要性とは?不要といわれる理由や年代別の選び方も解説
「民間の医療保険は必要なのか、それとも不要なのか」「どのような医療保険に加入すればよいのか」と悩んでいる人は多いでしょう。民間の医療保険が不要と考える方もいますが、公的医療保険のみでは賄いきれない医療費も存在します。…
医療保険の加入条件で知っておきたいこと
医療保険には加入条件があり、保険会社の審査により、その条件を満たしていると認められなければ加入できません。なぜ審査があるのか、何が審査され、どのような点に気をつければよいのか。医療保険の加入条件や審査について確認しておきましょう。 …
医療保険の保険料払込期間の決め方と注意点
医療保険の払込期間には、保険料を一生涯払い続ける「終身払い」や、決められた期間まで払い続ける「短期払い」があります。今回は医療保険の払込期間にスポットをあてて、払込期間の基礎知識や、終身払いと短期払いの特徴、 …
30代で医療保険は必要!その理由と選び方を徹底解説
結婚や出産、マイホームの購入など大きなライフイベントを迎えることが多い30代。収支に変化が起きやすいタイミングだからこそ、ケガや病気に対するリスクにもしっかりと備えておくことが大切です。 …
手術給付金ってどんな保障?
医療保険の保障の1つに、手術給付金があります。手術給付金とは、病気やケガで手術をした際に受け取れる一時金です。保険会社によって受け取れる条件や金額が異なりますので、医療保険を選ぶときには手術給付金に注目しておきましょう。 …
20代が選ぶべき生命保険とは?ライフステージ別の保険の選び方とポイント
20代で生命保険に加入すべきか迷っている方もいることでしょう。若い世代は保険の必要性を感じにくいかもしれませんが、将来のリスクに備えるためには早めの対策が肝心です。 …
医療保険の見直しで損しない!最適な選び方とタイミング
医療保険の見直しがなぜ必要なのか、見直しのタイミングや具体的な手順、注意点についてわかりやすく解説します。これを機に、自分に合った保障を再確認してみましょう。 …
他カテゴリのコラムを見る
チューリッヒ生命カスタマーケアセンター
0120-680-777
月~土午前9時~午後6時 ※日曜・祝日は除く
保険に関するご質問・ご相談など
お気軽にお電話ください。
専門のオペレーターが丁寧にお応えします!