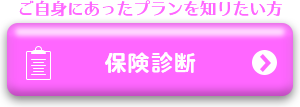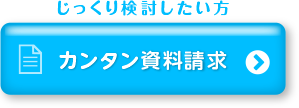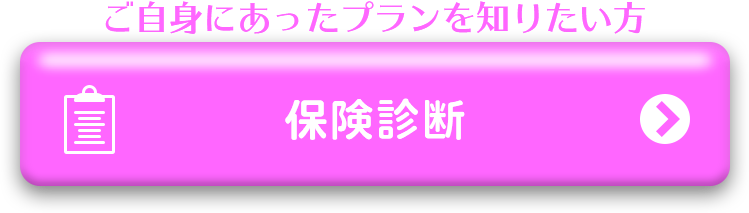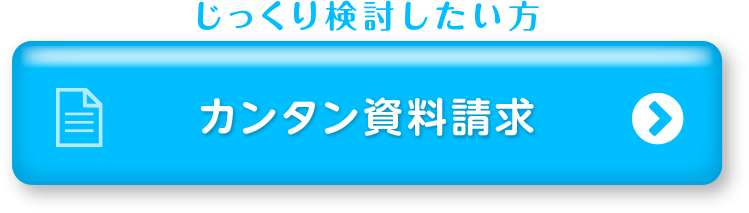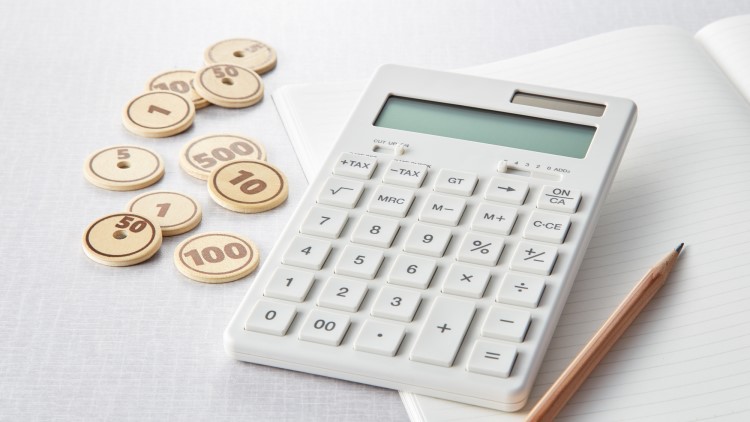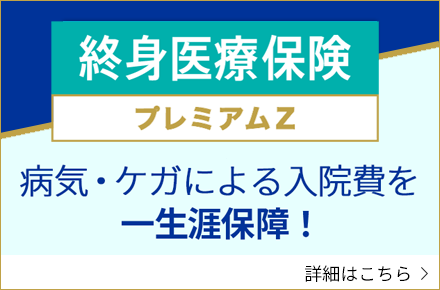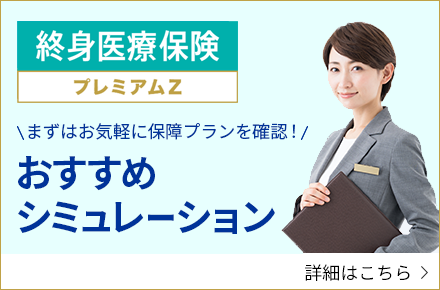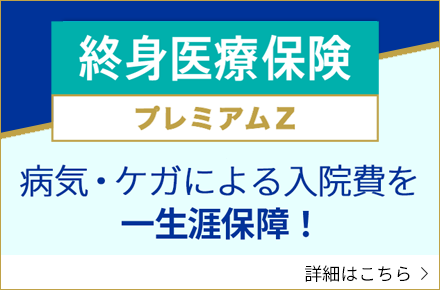医療保険の受取人は誰がなる?指定のルールから税金の違いまで詳しく解説
掲載日:2023/01/17 更新日:2025/08/15

医療保険に加入する際は、申込時に給付金の「受取人」を決める必要があります。受取人には誰を指定できるのでしょうか。
ここでは、医療保険の給付金を受け取るときに問題が起きないよう、受取人の決め方や税金の仕組みについて詳しく解説します。
- 医療保険の受取人は「被保険者」が一般的
- 被保険者は本人・配偶者・2親等以内の血族
- 本人に代わり請求を行う「指定代理人」も定められる
目次
1.医療保険の受取人になれるのは誰?
医療保険に加入する際は、給付金の受取人を指定します。受取人に指定できる人は、保険会社や保障プランによって異なるものの、最近では「被保険者」と決められていることが一般的です。
被保険者とは、病気やケガをしたときに保障を受けられる人、つまり保険をかけられている人のことを指します。
医療保険で被保険者になれるのは、契約者本人・配偶者・2親等以内の血族(父・母・子ども・兄弟姉妹・祖父母・孫)です。
なお、医療保険では被保険者が病気やケガで入院などをした場合に、下記のような給付金を受け取ることができます。
| 給付金 | どんなときに受け取れる |
|---|---|
| 入院給付金 | 入院したとき (支払限度日数あり) |
| 手術給付金 | 手術を受けたとき |
| 通院給付金 | 入院後に通院したとき |
| 延長入院給付金 | 支払限度日数を超えて入院したとき |
| 放射線治療給付金 | 放射線治療を受けたとき |
| 先進医療給付金 | 先進医療を受けたとき |
被保険者と受取人が同一であれば、加入している保険の内容を理解しているため給付金の請求をスムーズに行うことができます。しかし、受取人(被保険者)本人が意識不明の状態になるなど、自身で給付金を請求することが難しいケースもあります。
このようなときのために、医療保険では本人に代わって給付金の請求を行える「指定代理請求人」を設定できます。
1-1.指定代理請求人とは
指定代理請求人とは、受取人が自分で給付金の請求ができない事情がある場合に、本人に代わって保険会社に給付金の請求を行える人を指します。被保険者と受取人が同一となっている契約に限り、下記のようなケースにおいて給付金が代理で請求できるようになります。
<ケース1>
病気や事故などで意識不明状態となり、給付金を請求する意思表示ができない場合。
<ケース2>
保険会社が認める傷病名(がんなど)の告知や余命6ヶ月以内であることの告知を家族のみが受け、被保険者(受取人)本人には知らせていない場合。
指定代理請求人を指定できるのは契約者のみで、指定するには被保険者の同意を得る必要があります。また、被保険者の同意があれば途中で指定代理請求人を変更することも可能です。
指定方法は保険会社によって異なり、契約に「指定代理請求特約」を付加する会社と、契約時に指定代理請求人を指定する会社があります。
指定代理請求人として指定できる範囲は、被保険者の「戸籍上の配偶者」「直系血族」「兄弟姉妹」「被保険者と同居、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族」とされていることが一般的です。
しかし、同居要件なしだったり、事実婚・同性パートナー・婚約者も認められていたりと、指定代理請求人になれる人の範囲や条件は保険会社によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
>チューリッヒ生命の指定代理請求人の変更はこちらから
指定代理請求人を変更したいのですが、どうすればいいですか? | チューリッヒ生命
2. 医療保険の受取人によって税金の種類は変わる?

医療保険の給付金は基本的に非課税のため、医療保険の給付金を受け取ったときの確定申告は不要です。
ただし、確定申告によって医療費控除の適用を受ける場合は、支払った医療費から受け取った入院給付金の金額を差し引く必要があります。
また、受取人以外の人が受け取った場合や、身体の病気やケガに起因せず支払われた場合については相続税や所得税の課税対象となるため注意を払いましょう。
・相続税の対象になる場合…受取人が給付金を受け取る前に死亡し、遺族が代わりに受け取ったとき
・所得税の対象になる場合…契約者(=受取人)が健康お祝い金や解約払戻金を受け取ったとき
加えて、死亡保険金の場合は、契約者・被保険者・受取人の関係によって税金の種類が異なります。ここでは、3つのパターンを確認していきましょう。
2-1.「契約者=被保険者≠受取人」のときは相続税
契約者と被保険者が同一で受取人は別の人の場合、死亡保険金は相続財産として扱われるため、相続税の課税対象です。
死亡保険金にかかる相続税には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の人数」の金額を受け取った保険金から差し引くことができます。例えば、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人の場合、死亡保険金1,500万円までは非課税となる仕組みです。
ただし、前出した「受取人が医療保険の給付金を受け取る前に死亡し、遺族が代わりに受け取った場合」には、上記の非課税枠は適用されません。受け取った未請求の給付金すべてが相続税の課税対象となります。
2-2.「契約者=受取人」のときは所得税
契約者と受取人が同一で死亡保険金を受け取った場合は、所得税の課税対象となります。ただし、どのような所得としてみなされるかは死亡保険金の受け取り方によって異なります。
まず、死亡保険金を一時金として受け取った場合は、「一時所得」とみなされます。一時所得には特別控除(最高50万円)がありますので、「(死亡保険金-支払保険料-特別控除)× 2分の1」の計算式によって算出した金額に税金がかかる仕組みです。
また、医療保険によっては死亡保険金を年金形式で受け取ることも可能です。この場合、受け取った年金は「雑所得」とみなされます。
雑所得では、その年に受け取った年金からその金額に対応する支払保険料を差し引いた金額が課税対象となる仕組みです。ただし、支払保険料を差し引いた後のその金額が25万円以上となる場合は、保険会社によって10.21%の源泉徴収が行われます。
2-3.「契約者≠被保険者≠受取人」のときは贈与税
契約者も被保険者も受取人もすべて別の人の場合は、契約者から受取人にお金が贈与されたとみなされ、贈与税の課税対象となります。
贈与税では110万円の基礎控除がありますので、110万円を超えた分に税金が課される仕組みです。
3. 医療保険の受取人を変更したいときは
給付金の受取人が被保険者に指定されている商品については、受取人の変更を行うことはできません。しかし、受取人を自分で決められる保険では、被保険者の同意があれば変更可能です。
一般的に、受取人は以下の手順で変更できます。

受取人を変更する場合には、各社所定の手続きが必要です。
通常は書面での手続きとなりますが、なかには電話や契約者専用サイト上で変更手続きを完結できる保険会社もあります。手続き方法の詳細は、各保険会社のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
もし受取人が誰になっているかわからない場合は、下記のような方法で確認できます。
<受取人が誰かを確認する方法>
①保険証券
②契約者専用サイト
③保険会社から定期的に送付される通知 など
4.よくある質問

Q1:医療保険の受取人とは?
A:医療保険の受取人とは、被保険者が病気やケガによって給付金が支給される場合、その給付金を受け取る人のことです。受取人は、保険会社が定める所定の手続きを行うことによって給付金の受け取りが行えます。
Q2:医療保険の受取人は本人以外でもなれる?
A:受取人に指定できる人は、保険会社や保障プランによって異なるものの、最近では「被保険者」と決められていることが一般的です。ただし、被保険者が給付金の請求を行えないときのために、「指定代理請求人」を定めておくことが可能です。
Q3:医療保険の給付金を受取人以外が受け取った場合、税金はかかる?
A:医療保険の給付金は基本的に非課税ですが、受取人以外が受け取った場合は課税対象です。例えば、受取人が給付金を受け取る前に死亡し、遺族が代わりに受け取ったときは「相続税」の課税対象となります。
4.まとめ
医療保険の受取人を変更できるのは、受取人を自分で決められる商品の場合のみです。加入している保険や、これから加入する予定の保険がどのようなルールとなっているかは、「ご契約のしおり・約款」を確認するか、生命保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
被保険者=受取人と決められている場合は、自分で給付金を請求できない状態になる恐れがあるため、指定代理請求人の設定をしておくことをおすすめします。
なお、チューリッヒ生命では、所定の条件を満たす場合に「指定代理請求特約」を付加することが可能です。被保険者(受取人)本人が給付金を請求できない事態に備えて、ぜひ指定代理請求人を指定できる医療保険への加入を検討してみましょう。
※上記は一般的な内容です。保険の種類や呼称、保障内容等は商品によって異なりますので、実際にご加入いただく際は商品詳細をご確認のうえご契約ください。
【執筆・監修】

椿 慧理(つばき えり)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 1種外務員資格
- 内部管理責任者
立命館アジア太平洋大学卒業後、入行した銀行で10年間勤務。個人・法人営業として投資信託、保険、仕組債、外貨預金等の提案・販売を務める。現在は銀行での経験を活かし、金融専門ライターとして活動中。
X:https://twitter.com/tsubakieri88
ライター記事一覧 >
チューリッヒ生命カスタマーケアセンター
0120-680-777
月~土午前9時~午後6時 ※日曜・祝日は除く
保険に関するご質問・ご相談など
お気軽にお電話ください。
専門のオペレーターが丁寧にお応えします!