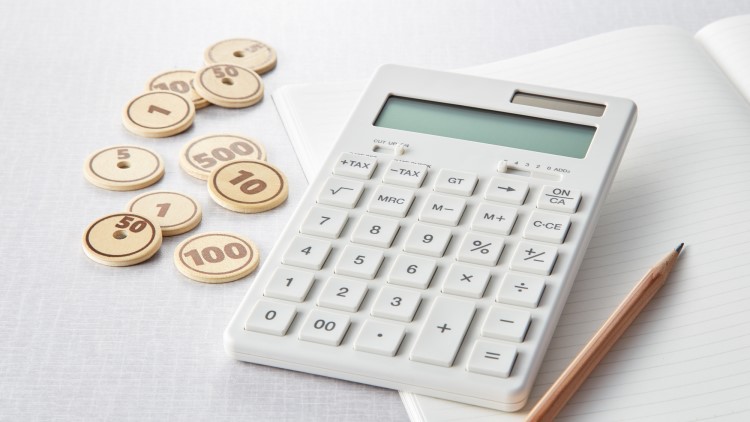死亡保険コラム
死亡保険の加入や見直しを検討している方や、死亡保険の基礎知識を身に付けたい方へ。
選ぶ時のポイントや、必要な金額などを詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。
終身保険のメリットとデメリットを知ろう!どんな人におすすめ?
終身保険をご検討中の方、メリットやデメリットについて理解できていますか? 終身保険は一生涯の契約となるため、慎重に選択する必要があるでしょう。このコラムでは、一般的な終身保険のメリット・デメリットから、保険料の支払方法別や商品種類別のメリット・デメリットまで、さまざまな角度からわかりやすく解説します。…
20代は生命保険に入るべき?保険の加入率やケース別の選び方をご紹介
20代になると学生から社会人になり、生命保険について考え始める時期です。しかし、「生命保険って本当に必要なの?」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。このコラムでは、そんな疑問を解消するために20代の生命保険の加入状況や、ライフステージに応じたおすすめの商品をご紹介します。…
結婚するなら生命保険を見直すべき?必要なチェックポイントをご紹介
「結婚」は、保険を見直す良いきっかけだといわれています。そこでここでは、結婚したときに見直しておきたい保障や保険の手続きのほか、おすすめの生命保険についてご紹介します。…
生命保険とは?種類や必要性について徹底解説!
自分に合った生命保険に入るためには保障の内容を理解しておくことが重要です。今回は生命保険の種類と必要性について詳しく解説します。生命保険の申し込みを検討している方、今加入している生命保険の見直しを考えている方はぜひ参考にしてください。…
生命保険の告知義務違反とは|必要な告知内容から違反時の対応まで解説
生命保険に加入する際には、既往症などの「告知」を行います。この告知内容に誤りがあった場合、「不慮の事故で本人が亡くなったのに、保険金が支払われない!」などの困った事態になる可能性も。…
生命保険の受取人は誰にする?税金や変更方法の違いを解説
生命保険に加入する場合は受取人を指定する必要がありますが、受取人の違いによって、保険金を受け取ったときにかかる税金も変わることをご存じでしょうか。この記事では、生命保険の受取人によって変わる税金について詳しく解説します。あわせて受取人に指定できる人の範囲や、契約後の受取人変更についてもご紹介します。…
死亡保険金はいくら必要なのか?決めるときのポイントを解説
「死亡保険金はいくら必要なのか」と想像してみても、なかなか明確な答えが出せないという人は多いでしょう。死亡保険金額は家族構成や資産状況などによって異なりますが、自身と生活環境が近い方の平均額を参考にすることで、目安を知ることができます。本記事では、…
生命保険のクーリング・オフは可能?期間や申請方法を紹介
生命保険は、いざというときに役立つ資金調達手段のひとつです。しかし、役に立つからと生命保険を契約したものの、保障内容を十分に理解できていなくて心配になってきた……と不安を感じている方もいるかもしれません。そんな方に知っていただきたいのが、…
生命保険はいらないと言われる理由を解説!加入の必要性や注意点を押さえて検討しよう
生命保険は病気やケガ、死亡時などに給付金や保険金が受け取れるため、もしものときのために加入を検討している人も多いでしょう。一方で、「生命保険はいらない」という意見もあり、 …
他カテゴリのコラムを見る
チューリッヒ生命カスタマーケアセンター
0120-680-777
月~土午前9時~午後6時 ※日曜・祝日は除く
保険に関するご質問・ご相談など
お気軽にお電話ください。
専門のオペレーターが丁寧にお応えします!